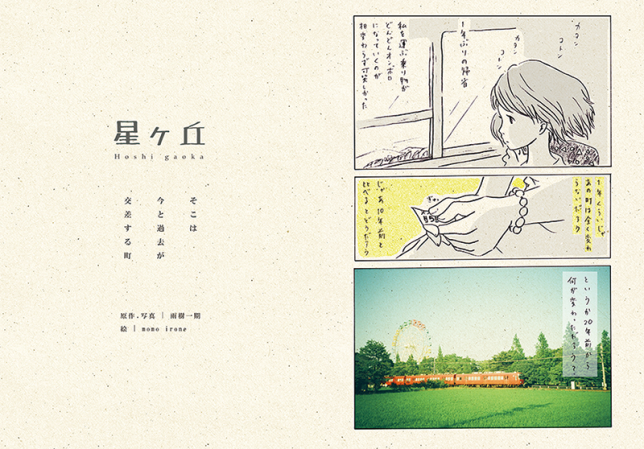短編小説 『祖母の後ろ姿』

僕の祖母は駄菓子屋を営んでいた。近所の悪ガキを怒ったり、泣いている子を励ましたり、下ネタを言って笑わせたり、誰にでも気さくに話しかける名物おばあちゃんだった。
みんな少しのお小遣いを持って、自分で計算して駄菓子を買っていた。お金がなくても、祖母に会いにくる子供がたくさんいた。
小学生の頃はたまり場になっていて、「ええなーお前んち。ばーちゃんオモロいし、駄菓子タダやし!」なんて言ってくる友人がいて、僕はこの駄菓子屋と祖母が誇らしかった。
だけど、中学生を卒業する頃には、みんな部活や塾に明け暮れていて、駄菓子屋に集まることもなく、誰もそんなことを言ってこなくなった。
僕はというと、透明のケースに入った煎餅を一つ10円で売っているなんて恥ずかしいと思っていた。
小学生の頃はいつもお店の中から、つまり正面から祖母の顔を見ていたけど、中学になってそれが後ろ姿に変わった。
高校になってからは、子供たちの相手をする姿は見れなくなった。
今、ショッピングモールなどで『駄菓子ショップ』を見かけることがあるけど、そこにいるのはただの店員さん。消費税だって取られる。昔のお菓子は懐かしいけど、それは袋に入ったお菓子で、透明のケースに入れられた10円の煎餅はない。
懐かしいというのは商品であって、そこにある空気は全くの別物だ。自分で小遣いを計算して買いにくる子供もいなければ、オモロいばーちゃんもいない。
わざとらしくレトロ感が演出されているだけで、そこには何の会話もない。
それがダメというわけじゃないけど、全くの別物だ。
大切なものは、その時は大切だとは気付かない。失ってすぐに気付くこともあれば、少しの時間をおいて気付くこともある。
祖母の後ろ姿の向こうにはいつも笑顔の子供たちがいた。
僕はいま、それがとっても誇らしい。